クロモリジンAHSSMDその働きは多岐にわたります |
| 注目を浴びるアラビノキシラン・リグナン |
| クマ笹には、タンパク質の主要な成分であるアミノ酸が24種類も含まれており、なかでも体内では、合成できず食物から取るしかない必須アミノ酸8種類のうち7種類までが含まれています。ほかにも、体内で免疫を担当するマクロファージという細胞を活性化するリグニンという物質が、含まれていることも発見されています。「マクロファージ」は、体内に侵入した有害な物質を食べてしまう性質をもっており、インフルエンザウイルスや、その他のウィルス天敵にもなるのでは、と期待されています。笹の成分の中で最も注目されているのが、多糖体アラピノキシランです。糖は、ブドウ糖に代表される単糖類、オリブ糖などの小糖類、食物繊維などの多糖類の3種類に分類されます。多糖類は、いくつかの単糖類が紡合してできたものです。クマ笹に特に含まれている多糖類の主な成分が「アラピノキシラン」というものです。最近になって、人の免疫を活性化する性質があることが分かり、注目を浴びています。 |
| 循環多段式加圧抽出法によるクマイ笹エキスの高抗酸化力 |
「循環多段式加圧抽出法」(特許)は、植物の細胞膜に圧力をかけて破リ、従来の数倍から数十倍の成分(ちから)を細山することができます。この循環多段式加圧抽出法によって抽出されたクマイ笹エキスには、抗酸化力がビタミンCの約40倍もあり、黄色ブドウ球菌や緑膿菌などに対する殺菌作用があることが、検査機問の試験で証明されています。このことをブドウ球菌の研究で国際的な権威である東京慈恵会医科大学名誉教授の近藤勇先生にお話ししたところ、近藤先生ご白身の手で実験をしていた
だくことができました。その結果、驚くべきことに、クマイ笹エキスほ、ブドウ球菌や緑膿菌だけではなくピロリ菌に対する強力な殺菌力をもっていることが明らかになったのでした。
|
ヘリコバクター・ピロリ菌のしっぽの部分 (鞭毛)を溶かして、殺してしまいます。 |
| AHSSはピロリ菌の遺伝子に作用し細胞分裂を止める |
| 2005年のノーベル生理学・医学賞がオーストラリアのバリー・J・マーシャル教授(西オーストラリア大学)とJ・ロビン・ハウォーレン医師に授与されたことがTVや新聞等で報道され、話題を呼びました。1982年に、ヘリコバクター・ピロリ菌というらせん状の細菌が胃の中に生息して、胃潰瘍や胃がんなどの原因になっていることを発見し、それを証明した功績に対して授与されたものです。今月号は、東京慈恵会医科大学名誉教授・医学博士の近藤勇先生にヘリコバクター・ピロリ菌についてうかがいました。 |
| 期待されるクマイ笹エキスの高い殺菌力 |
| 循環多段式加圧抽出法はによって抽出されたクマイ笹エキスが、黄色ブドウ球菌や緑膿菌に対して強い殺菌力持つとされ、さっそく研究室に送られてきたクマイ笹エキスを黄色ブドウ球菌数十株に加えてみました。すると、短時間でブドウ球菌全株が殺菌されたことが確認できました。黄色ブドウ球菌には、院内感染で社会問題となったMRSA (メチシリン耐牲黄色ブドウ球菌)がありますが、クマイ笹エキスの殺菌がメチシリン耐性に関係なく、同等に見られたことは特筆に値します。 |

東京慈恵会医科大学名誉教授・医学博士
近藤勇 こんとう・いさむ
一九一八年、岩手県生まれ 慈恵会医科
大学医学部卒業「医学博士。東京慈恵会
医科大学講師、助教授を経て一九八七年
に同大学細胞学教室教授。名誉教授。一
九ハニ年から大正製薬総合研究所所長を
十年間務める。ブドウ球菌の毒素の研究
では国際的な権威。ブドウ球菌研究会名
誉会員、日本細菌学会名誉会員、日本電子顕微鏡学会名誉会員。一九七八年に第十四回小島三郎記念文化賞を受賞。 |
|
クマイ笹エキスはピロリ菌を除菌できる
クマイ笹エキスの実験をコレラ菌とピロリ菌に対して行なうと、現在、調べたかぎりで最も高い殺菌性を示しました。コレラ菌とピロリ菌は、菌体の一端にタンパク性の鞘(さや)に包まれた鞭毛を持っているのが特徴です。クマイ笹エキスをピロリ菌に加えると、簡単に死滅したコレラ菌と同じように、ビロリ菌が活動する時に使う鞭毛をおおう鞘がコイル状にほどけて鞭毛があらわれ、菌体もバルーン状にふくれたり、細かい小胞になってくずれました。
この変化は電子顕微鏡で観察され、それを平成13年9 月にドイツのフライプルグで開催された国際ピロリ菌学会で発表したところ、各国の研究者たちに衝撃を与えました。さらに、わたしたちは、ピロリ菌を殺菌するクマイ笹エキス中のクロモリジンという物質を濃縮、精製し、その化学構造を明らかにして、平成16年9月にオーストリアのウィーンで開催された国際ピロリ菌学会で発表しました。クマイ笹エキスが、ピロリ菌の除菌に役立つであろうクロモリジンを多量に合むことは、とても貴重であると考えます。 |
| ピロリ菌撮影:近藤勇名誉教授 |
ピロリ菌
|
溶けた鞭毛鞘
|
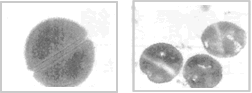
正常なブドウ球菌の細胞分裂(左)と、
クマイ笹エキスによって分裂が止まった状態(右) |
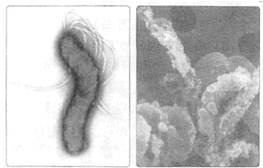
正常なピロリ薗(左)と、
クマイ笹エキスによって死滅した状態(右) |
|
近藤勇・東京慈恵会医科大学名誉教授が国際学会で世界初の研究発表 |
| 欧米の研究者から質問相次ぐ |
|
|
| 発表パネルの前の近藤勇名誉教授 |
 |
三木所長の研究所ではAHSSの
構造解析が進む |
平成14(2002)年10月16日〜19日に、つくば国際会議場において第10回国際ブドウ球菌シンポジウム(International
Symposium on Stashylococciand Staphylococcal Infections;ISSSI)が開催され、近藤勇・東京慈恵会医科大学名誉教授が「AH
SS」による最新の研究発表をされました。
今回の発表は、黄色ブドウ球菌やヘリコバクター・ピロリなどの細菌が細胞分裂をするときに働く遺伝子
ftsZおよびftsAの発現を、AHSSの成分が阻害し、いずれの細菌も死滅させてしまう事実を世界で始めて発見し、検証したものです。
細菌の遺伝子に作用して、細胞分裂を阻害する物質が
植物成分から発見されたのは世界で始めてで、今回の研究発表では、AHSSが作用して細胞分裂が中断した状態の黄色ブドウ球菌やヘリコバクター・ピロリ
の電子顕微鏡写真も公表されました。
この画期的な発表に「AHS Sの成分のなかで細菌に作用する物質は特定されているか」など欧米の研究者から質問が相次ぎ、近藤名誉教授は現在までに構造解析されているいくつかの成分について説明されました。
これまでの研究で、AHSSを黄色ブドウ球菌やピロリ菌に作用させると、ごく薄い濃度でも死滅する事がわかっていますが、近藤名誉教授と共同研究しているバイオス医科学研究所(神奈川県平塚市)の三木敬三郎所長によると、遺伝子に作用する物質も含めて細菌に有意に作用するAHSSの成分は14〜15種類あると考えられます。このうち、これまでにほぼ構造解析が終わったものは次の3種類です。
| (1)細胞膜と細胞壁を破壊する成分 |
(2)遺伝子の合成を阻害する成分 |
(3)細胞壁を壊す成分 |
| 抗生物質のなかにも細菌の細胞膜に入り込んで細胞膜生成を阻害するものがあるが、AHSSのこの成分は細胞の外から直接、細胞壁と細胞膜を破壊すると考えられる。ポリフェノール・タイプの有機化合物。 |
化学合成された抗がん剤にもがん遺伝子に対して同様な作用をするものがあるが、副作用が強いなどの問題があるゥ AHSSの成分から、副作用のない抗がん剤も期待できる。核酸に近い有機化合物。
|
(1)の成分とは別に、分裂期の細胞壁だけに特異的に作用し、細胞壁の生合成を破壊すると考えられる。細胞壁は人の細胞にはないので、細菌だけを攻撃する副作用のない優れた医薬の開発が期待できる。分子量200近くの低分子化合物。 |
|
| ピロリ殺菌力はヨーグルトなどの1万倍以上 |
| なお、ピロリ菌の殺菌作用はヨーグルトやココアなども話題になっていますが、三木所長は「私たちもさまざまな殺菌作用を実験してきましたが、AHSSは別格です。精製した状態ならほかのものの1万倍以上の殺菌力をもっているだろう」と推測されています。研究課題はまだ多く残されていますが、三木先生は「AHSSは研究者にとって宝の山。この研究から、まったく新しい天然の抗生物質が誕生することを夢見ています」と語っておられます。 |
「ピロリ菌」 欧米に比べて、日本でピロリ菌の恐さが理解されていないのは、そのかわいらしい名前のせい・・・・・・・・ |
| コレラ菌・サルモネラ菌・エイズウィルスなどの名前を聞くと、恐そうで、「警戒しなくては……」という気持ちになります。それに比べて「ピロリ菌」という名前にはどこか愛嬌があって、「胃のなかでイタズラする菌」くらいのイメージしか持っていない人が多いようです。
しかし名前のイメージとは裏腹にピロリ菌は恐い細菌です。 胃腸疾患の多くがピロリ菌の感染で起こることがあきらかになり、データによると日本人の2人に1人が感染者と考えられています。 |
| ピロリ菌保菌者は胃腸病になりやすい |
| 日本人の2人に1人が感染者 |
| 慢性胃炎の患者 → |
70〜90%が感染 |
| 胃潰瘍の患者 → |
70〜90%が感染 |
| 胃がんの患者 → |
60〜100%が感染 ↓ |
ピロリ菌はその表面にある細い繊維状のもの(アドヘジン)を使い、粘液細胞にしっかり定着します。ウレアーゼという酵素が尿素からつくるアンモニアは強いアルカリ性なので、細胞に炎症を起こします。
この時、インターロイキン8などのサイトカインと呼ばれる物質を 大量に作ります。そして、インターロイキン8が、活性酸素(フリーラジカル)と反応して、一酸化窒素などの猛毒に変化します。
これにより 細胞障害を起こすのです。 また、ピロリ菌には 細胞を死滅・消滅させたり、自己免疫反応を起こす可能性も指摘されており、ピロリ菌によって胃の細胞を壊死させられ
粘膜に覆われない部分が、胃の強い酸に侵され潰瘍が進むと考えられています。このような事から ピロリ菌は 早急に除菌・抑制処置を必要とする非常に恐い菌であるのです。 |
| ピロリの除菌療法 |
抗生物質 薬剤は正常細胞にもダメージを与える副作用があります。抗生物質をむやみに使うと、抗生物質が効かない菌=耐性菌が現れて、抗生物質その物が無効になってしまう恐れがあります。
※抗生物質と細菌の「いたちごっこ」で、身体への悪影響も懸念される。 |
| 安全な除菌へ |
細菌の抗生物質の戦いは、現在のところは耐性菌が一歩リードしている様相で人類はこのまま“永遠の戦い”を続けるかどうか、それとも戦略の基本的な見直しを行うべきか、という選択を迫られていると言っていいでしょう。
また最近になって、抗生物質による副作用が深刻な病気を引き起こすこともわかってきました。これらの事から「新世代の抗生物質」は容易には耐性菌が生まれず、しかも、安全性がしっかり確認されたものでなければならないことは明らかです。 |